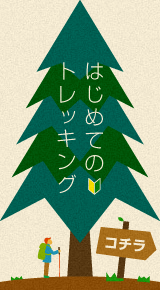- 体感温度
- 温度計で測定される気温とは別で、体に直接感じる温度のこと。体が濡れていたり強風が吹くことで下がり、風速1mにつき体感温度は1℃程下がる。
- 脱水症
- 汗のかき過ぎや水分摂取が足りずに、体内の水分が少なくなってしまう症状。足がつったり、脱力感などの症状がでることもある。脳梗塞の原因にもなる。
- ダイニーマ®
- しなやかで水に浮くほど軽い高強力ポリエチレン繊維。ケブラー®よりも引っ張り強度が高く、耐摩耗性や耐候性などにも優れます。スリングなどに使用しています。 他の素材に補強として交織され、軽量性を追求したバックオアックのライトウェイト・シリーズなどにも使用しています。
- ダッチオーブン
- 鋳鉄製の鍋。厚く蓋が重いので、保温性に優れ、煮込み料理やローストに向いている。キャンプ料理に欠かせない調理器具。
- タープ
- 日よけ、雨よけのナイロンシート。テントを張る場所が限られる沢登りなどでは、小型のタープだけを持っていくこともある。大型のものはキャンプなどで使われる。
- 地形図
- 国土地理院発行の2万5000分の1または5万分の1の地形図のこと。ガイドマップのようにコースタイムの記載はないが、等高線などからの地形を読むのに適している。
- 池塘(ちとう)
- 高層湿原にある小さな池。なんらかの理由によって、湿原のなかに植物が生育できない場所が生まれ、そこが湿原の発達から取り残されてできる。数多くの水生生物が成育している。
- 通気性
- 透湿性とは違い、ウエア内の空気(運動により過剰に発生した熱気)を放出する性能のことを言い、防水透湿素材に適度な通気性を付与することで、生地自体が換気機能を持ち、体温の上昇を押さえウエア内の蒸れを解消します。
- ツエルト
- 登山用の小型軽量テントのこと。一時的に雨風をしのぐためにかぶったり、木の間やトレッキングポールを使って張ることができる。小さくて携帯しやすいので、一般的には万が一の不時露営(ビバーク)の際に有効。
- つづら折り
- 山腹の急斜面をジグザグにたどる坂道。
- 吊尾根(つりおね)
- 近接したふたつの頂上を結ぶ稜線が、吊り橋を架けたように弧を描くところ。鹿島槍ヶ岳の南峰と北峰を結ぶ尾根など。
- 出合(であい)
- 2つの沢が合流するところ。また、登山道から目的の沢に入る地点のこと。
- 停滞
- 悪天候などのために行動できず、その場(山小屋やキャンプ地)にとどまること。沈殿ともいう。
- 低体温症
- 体が作る熱エネルギーよりも、水温や気温によって奪われる熱が大きくなって、体温が下がり続けてしまうこと。唇が紫色になったり、震えが止まらないなどの症状が出る。ひどい場合は動けなくなり、命にもかかわる。
- ディパック
- 日帰りハイキングに使うような小型のザックのこと。
- デポ
- 装備や食料の入った荷物をいったん置いていくこと。また、長期にわたる冬山登山などのために、シーズン前に荷物だけをルート上の非難小屋などにあらかじめ置いていくこと。
- デブリ
- 雪崩などで落ちて積もった雪の塊。
- 鉄砲水(てっぽうみず)
- 急激に増水した雨水が土砂などをともなって川や沢を激しく流れ下るもの。集中豪雨や台風、夕立などによっても起こる。
- デリュージDWR
- パタゴニアが独自に開発したデリュージDWR(耐久性撥水)加工は、一般のDWR(耐久性撥水)加工に比べて効果の持続力が高く、デリュージDWR加工が施されたウェアは、長年使用しても新品の時と同じ撥水の機能を発揮します。
- テルモス
- 携行できる金属製魔法瓶のこと。もともとはドイツのメーカー名から。
- テン場
- テント場の略。テントの設営可能な場所。
- 透湿性
- ウエア内の蒸れ(水蒸気)を放出する性能のことを言い、生地が24時間に放出した水分量(g/m²/24hrs)で表します。
- 透湿性防水素材
- 雨具などで、雨などの水は内側に通さず、内側からの水蒸気は外に逃すような構造になっている素材。ゴアテックスが有名だが、各社からさまざまな素材が出ている。
- 登山届
- 入山から下山までの登山計画を記した書類。登山計画書や入山届けともいう。登山を始める前に、登山口や入山案内所などに設置されている登山ポストに投函する。登山届を提出することで、万が一遭難や事故などが起こった場合に、スムーズな捜索や救助要請に役立。オンラインで提出できる地域もある。
- 徒渉(としょう)
- 水流を徒歩で対岸に渡ること。飛び石で渡れる場所もあれば、腰くらいまで水に浸かることもある。水量は季節や天候によって大きく変わる。
- トラバース
- 「横切る」の意味。山の斜面や岩場を直登するのではなく、水平方向に横へ移動すること。ピークへのアップダウンを避けて山腹を巻く場合も。
- 取りつく
- 尾根や岩場など、ルートの出だしとなる地点(取り付き点)から登り始めること。
- トレイル
- 人や動物によって山中につけられた道、踏み跡。登山道を指すことが多い。トレースもほぼ同様の意味で使われる。
- トレイルラン
- 山道を歩かないで走る登山形態。トレランと略すこともある。日本各地で大会も行われている。
- トレッキング
- 本来は海外の山岳地帯で行われる比較的長期間の徒歩旅行のこと。登頂を目的とせず、歩くことを楽しむのが特徴。最近では、日本国内での山麓周遊ハイキングなどを含む。
- トレッキングシューズ
- ハイキングや低山の登山に使う軽登山靴のこと。スニーカーのような簡単なものから本格的な革製のものまでを含むことがある。
- トレッキングポール
- 山登りで使う杖のこと。これをつきながら歩くと足の負担が軽くなる。また、足場の悪いトレイルでも重心がぶれにくいので、疲労感が軽減できる。両手にストックを持って歩くことをダブルストックという。ストックを突いた穴が登山道を荒らすこともある。
Outdoor Dictionary
home > アウトドア用語大辞典 > た